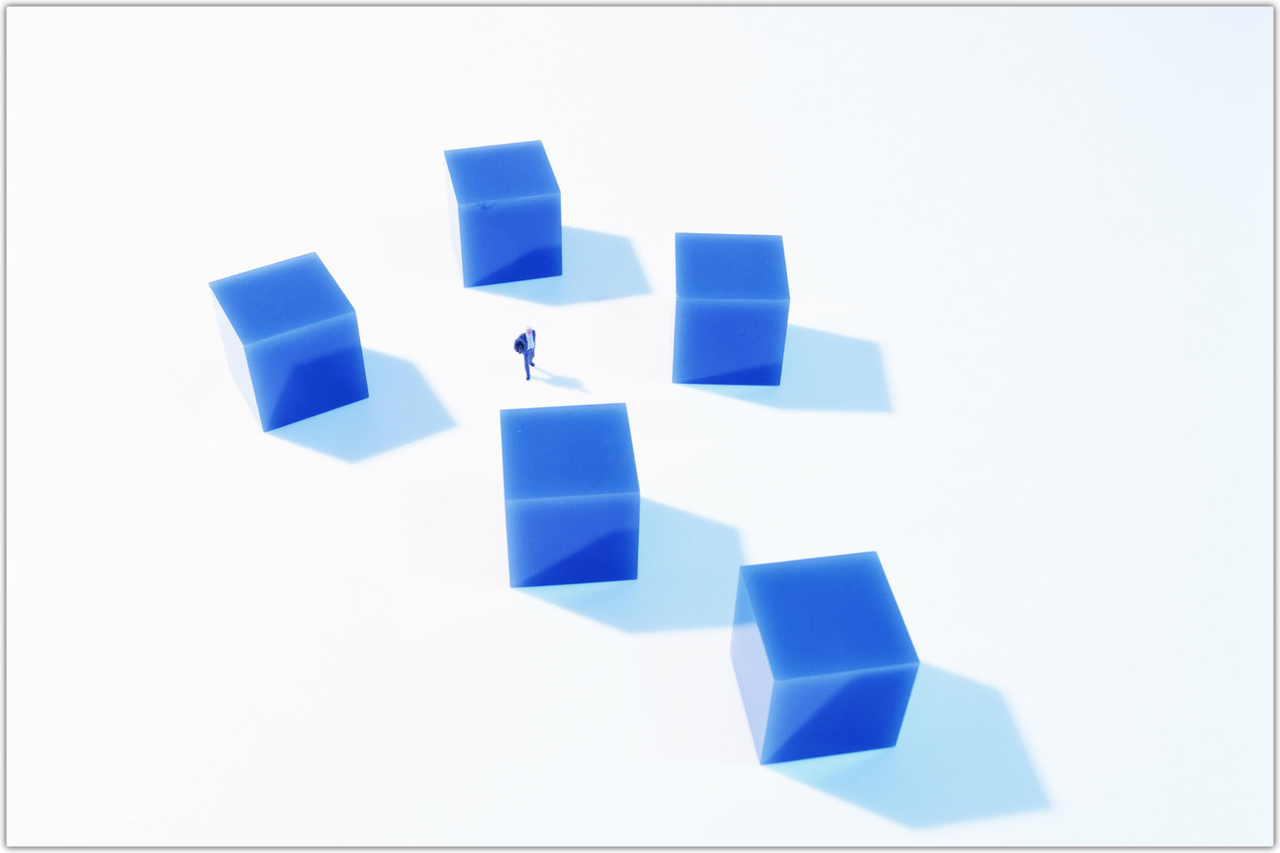家庭裁判所での相続放棄の申述手続
家庭裁判所での相続放棄の申述手続きについて、相続放棄の意義や効果、必要書類、手続きの流れ等、相続放棄の概要を案内したページです。
相続放棄の申述とは?
相続人が相続放棄をしたい場合、相続放棄申述書に戸籍等の必要書類を添えて家庭裁判所に申立てをしなければなりません。この家庭裁判所への相続放棄の申立てを相続放棄の申述といいます。
そもそも相続放棄って何?
相続放棄とは、相続財産の全て(プラスの遺産もマイナスの遺産も全部)を相続しない旨の意思表示をいいます。
相続により取得する財産は、プラスの財産(不動産・預貯金・現金等)だけではありません。マイナスの財産(借金や連帯保証人の地位等)も含まれます。
従って、被相続人(お亡くなりになった方)が多額の借金を抱えていた場合や連帯保証人になっていた場合には、相続人は被相続人の借金を返済する責任や連帯保証人の地位を相続により引き継いでしまうことになります。
被相続人の借金等のマイナスの遺産を相続したくない場合は、家庭裁判所で相続放棄の申述手続きをすることで、被相続人のマイナスの遺産を相続することを避けられます。
なお、相続放棄をするとマイナスの遺産のみならずプラスの遺産も相続することはできなくなります。
従って、被相続人のプラスの遺産とマイナスの遺産をよく調査してから相続放棄をするか否かを判断するのがベターです。
相続放棄の効果
相続放棄が認められると以下の効果が発生します。
相続放棄をした者は、その相続に関して、初めから相続人とならなかったこととみなされます(民法939条)。
→よって、被相続人の遺産を一切相続しません。
→また、代襲相続は認められません(民法887条2項本文・889条2項)ので、相続放棄をした人の子や孫が代わって相続人となることはありません。
相続放棄の方法
○期間
→相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内(民法915条1項)
○方式
→被相続人(亡くなられた方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄申述書や戸籍等の書類を提出して申立てます。
○必要書類
1.相続放棄申述書(800円の収入印紙を貼付します)
2.被相続人の戸籍・除籍、住民票の除票又は戸籍の附票
3.相続人の戸籍謄本
4.郵便切手(枚数は家庭裁判所により異なります。)
大阪家庭裁判所の場合は、110円切手5枚
※必要書類の内容を詳しく知りたい方は、相続放棄の必要書類のページをご覧ください。
相続放棄の手続きの流れ
相続放棄手続きの大まかな流れは以下のようになります。
1.戸籍等の必要書類を取得します。
▼
2.相続放棄申述書を作成し、800円の収入印紙を貼ります。
▼
3.家庭裁判所へ申立てます。
▼
4.家庭裁判所からの一定の照会事項に対して回答します。
▼
5.問題がなければ家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されます。
▼
6.家庭裁判所から相続放棄の申述を受理した旨の通知書が送られてきたら手続きは終了です。
▼
7.必要に応じ相続放棄申述受理証明書の交付を受け、債権者に提示(送付)します。
※相続放棄の手続きの流れについて詳しく知りたい方は、相続放棄の手続きの流れのページをご覧ください。
相続放棄よくある質問
被相続人の遺産について、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか明らかではなく、調査するのに時間がかかってしまい熟慮期間の3ヶ月を過ぎてしまいそうなんですけど・・・
このような場合は、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てた上で、相続財産を調査し、マイナスの財産が多いと判明した時点で相続放棄の申述をします。
相続放棄をすると、生命保険金や遺族年金は受け取ることはできなくなるの?
生命保険金については、受取人として特定の相続人が指定してある場合には、その相続人の固有の財産となりますので、相続放棄をしても受け取ることができます。
遺族年金についても各法律により遺族が受給権者として定められており、遺族の固有の権利となりますので、相続放棄をしても受け取ることができます。
主人が多額の借金を残して亡くなりましたので、配偶者である私と子供(未成年)が相続放棄をしようと考えております。この場合、私が未成年の子供を代理して相続放棄手続きをすることができますか?
親権者が未成年の子全員と同時に相続放棄をする場合には、利益相反行為(民法826条)に該当しないので、未成年の子供を代理して相続放棄手続きをすることができます(最高裁判所昭和53年2月24日判決)。
被相続人の遺産について、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか明らかではなく、調査するのに時間がかかってしまい熟慮期間の3ヶ月を過ぎてしまいそうなんですけど・・・
このような場合は、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てた上で、相続財産を調査し、マイナスの財産が多いと判明した時点で相続放棄の申述をします。
父が亡くなって3ヶ月経過してからサラ金業者から督促状が届き、この時に初めて父に借金があることを知りました。
この場合、3か月を過ぎているので相続放棄はできないのですか?
相続放棄の熟慮期間である3か月は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から起算されますが、この「自己のために相続の開始があったことを知った時」については「相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識したときまたは通常これを認識しうべき時」(最高裁判所昭和59年4月27日判決)と解されていますので、ご質問の場合には相続放棄ができると考えられます。
※3ヶ月を過ぎた相続放棄について詳しく知りたい方は、3ヶ月経過後の相続放棄のページをご覧ください。
お問合せ・ご相談はこちら

お気軽にお問合せください